終活で考えたい“公正証書遺言” 近年、家族に負担をかけないために、葬儀や相続の準備を進める「終活」に取り組む方が増えています。 特に、親の相続で苦労した経験がある50代・60代の方から、「相続の準備をどうすればいいのか?」という相談が寄せられることが多くなっています。 そんな相続の不安を解決する手段のひとつが、「公正証書遺言」です。 本記事では、公正証書遺言の基本、メリット・デメリット、作成手順、費用、遺言がない場合のトラブル事例について詳しく解説します。 大切な家族にスムーズに遺産を引き継ぎ、安心して最期を迎えるために、公正証書遺言を検討してみましょう。 公正証書遺言とは?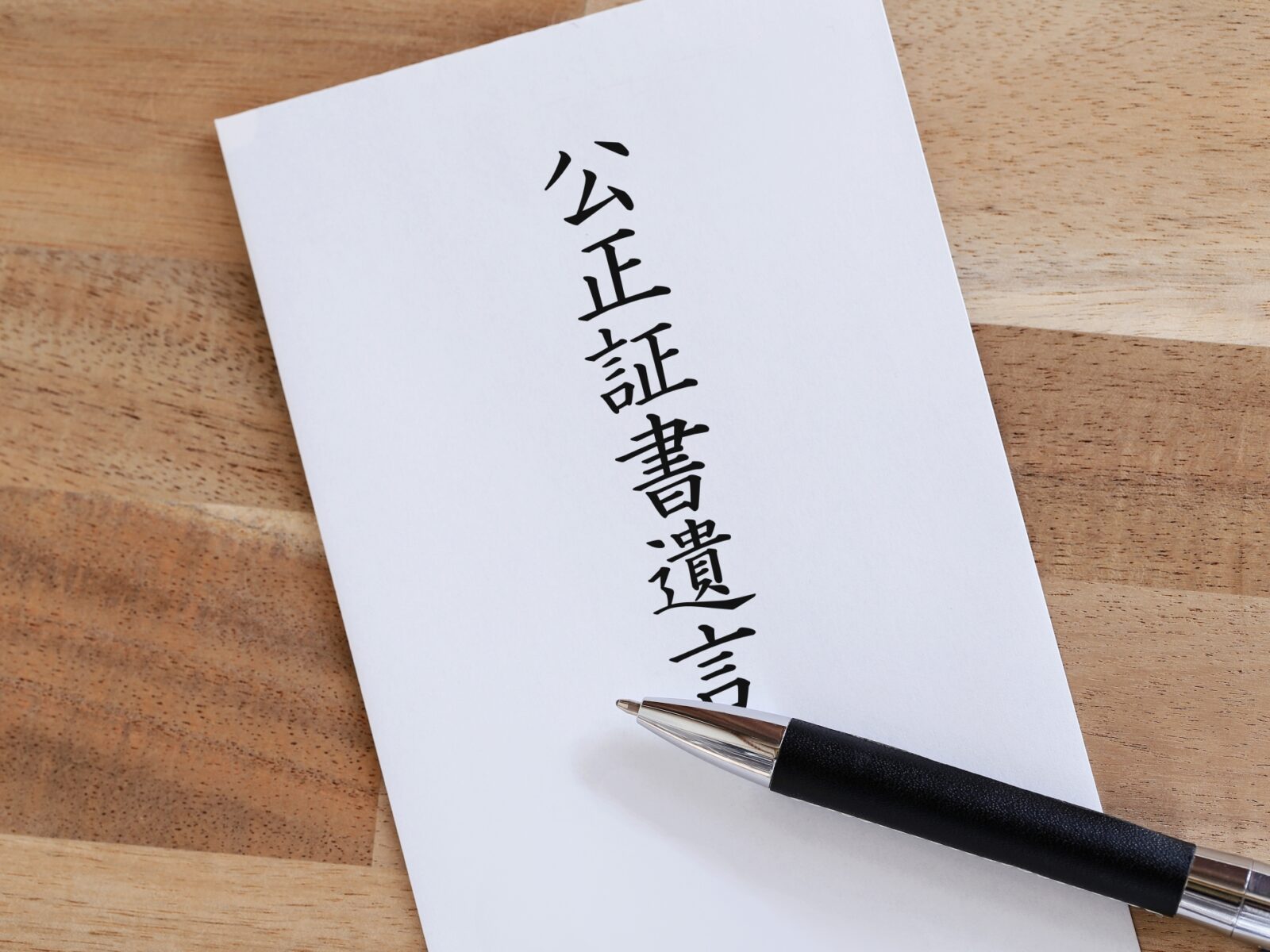 公正証書遺言とは、公証人が作成し、公証役場で保管される法的に有効な遺言書のことです。 遺言者の意思を公証人が確認し、適正な形で記録するため、無効となるリスクが極めて低いのが特徴です。 家族間のトラブルを防ぎ、安心して遺産を引き継ぐために、多くの方が選んでいます。 遺言の種類と比較遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ特徴があります。
🔹 自筆証書遺言 🔹 秘密証書遺言 🔹 公正証書遺言 公正証書遺言が選ばれる理由公正証書遺言が多くの方に選ばれるのは、以下のメリットがあるためです。 ✅ 法的に確実 → 公証人が作成し、無効リスクがほぼゼロ 公正証書遺言は、多くの財産を持つ方や、相続人間でトラブルを避けたい方、確実に遺産を分配したい方に特におすすめの方法です。 公正証書遺言を作成しなかった場合のトラブル事例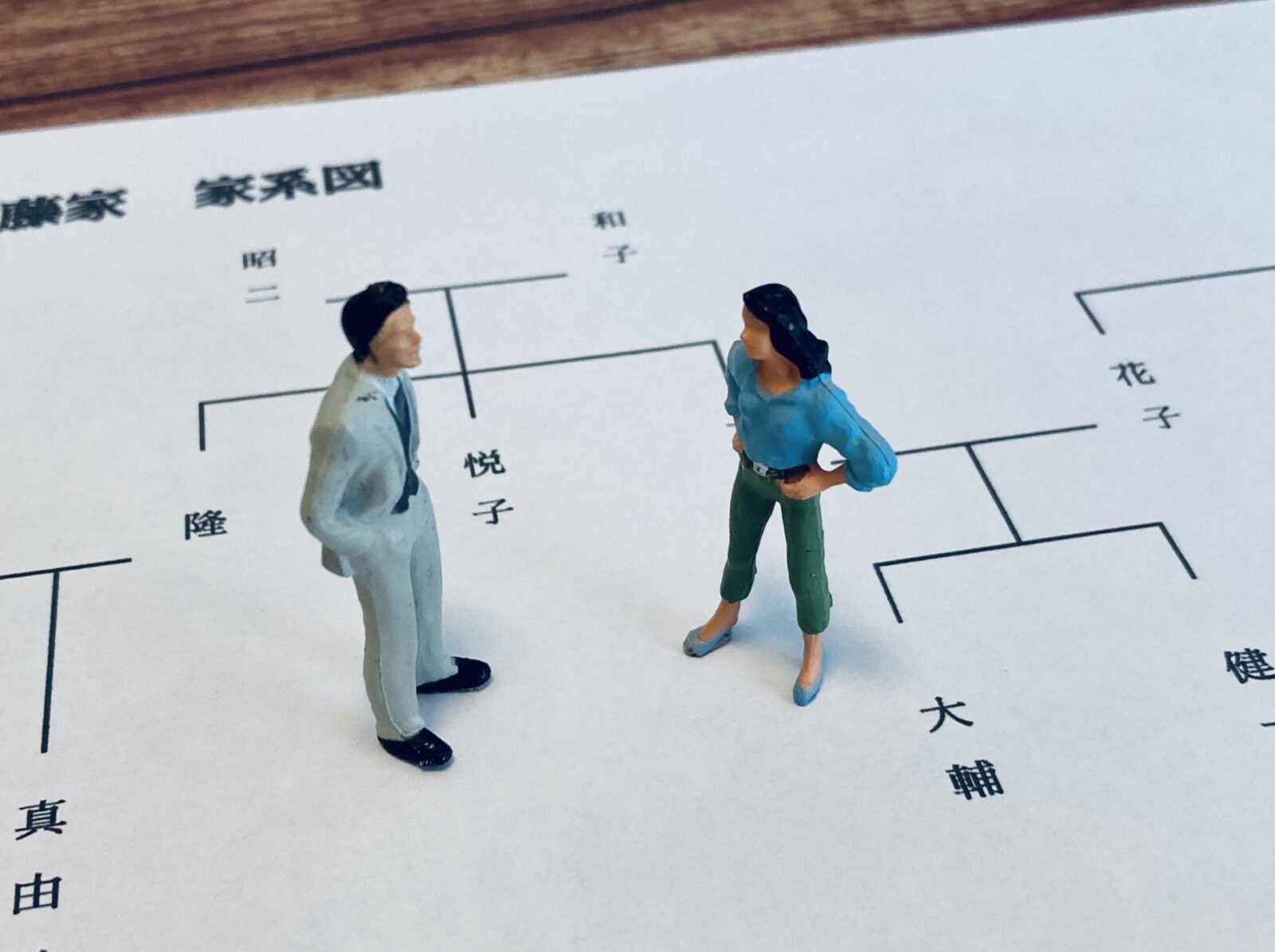 🔴 家族間の相続争い 🔴 配偶者の生活が困難に 🔴 事業や不動産の管理が混乱 故人が事業や不動産を所有していた場合、誰が管理・継承するのかが不明確になり、事業が混乱することがあります。事業を起こしている方、複数の不動産を所有している方は、公正証書遺言の作成が必須と言えるでしょう。 公正証書遺言の作成の手順と費用のめやす 公正証書遺言を作成するには、公証役場で手続きを行う必要があり、一定の費用がかかります。作成の手順と費用のめやすをまとめました。 公正証書遺言の作成の手順1️⃣ 遺言の内容を決める 必要な費用(めやす)
公正証書遺言を作成する際の注意点公正証書遺言を作成する際には、以下の点に注意しましょう。 1. 証人になれない人がいる遺言を作成する際には、証人が2名必要ですが、以下の人は証人になれません。
証人を依頼する際は、このルールを守ることが大切です。 2. 遺言執行者を決めるとスムーズ遺言の内容を確実に実行するために、「遺言執行者」を指定しておくと安心です。 3. 相続人の「遺留分」に配慮する一定の相続人には、法律で最低限の遺産を受け取る権利(遺留分)が保障されています。 4. 一度作成した遺言は簡単に変更できない公正証書遺言を修正する場合は、新たに作成し直す必要があります。 遺言を作成する際は、これらのポイントに気をつけながら、家族の状況や希望をしっかり考慮することが大切です。 まとめ:公正証書遺言で“安心”を手に入れる公正証書遺言は、法的に確実で安全に保管される、最も信頼性の高い遺言書です。 📌 家族の負担を減らすために、早めの準備をおすすめします! 仙台典礼のてんれい会員様特典として、相続や遺言に関するご相談(初回無料)を承っています。 |
お役立ち情報
