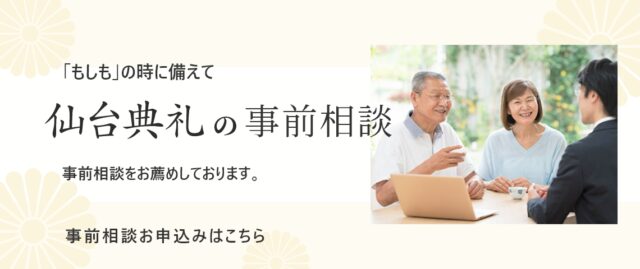身近な人の訃報は、多くの場合、思いがけないタイミングで訪れます。急な容体の変化や事故など、心の準備ができていないまま喪主を務めることになる方も少なくありません。まずは深呼吸をひとつ。大切なのは「今やるべきこと」を落ち着いて確認し、順番に進めることです。
本記事では、初めて喪主を務める方に向けて、3日間を目安にやることを時系列のチェックリストで整理しました。流れを知っておくことで、必要以上に慌てずに対応できます。
喪主を務めると決まったら、まず確認すべき3つのこと
最初の一歩で迷わないために、以下の3点を先に押さえましょう。ここが決まると、その後の段取りがぐっとスムーズになります。
1. 喪主がまず決めるべき安置先
喪主になったら最初に故人の安置先を決めます。自宅安置は家族がゆっくり過ごせますが、室内の温度管理や近隣への配慮が必要です。葬儀会館安置は設備が整い、家族の負担を軽減できますので、昨今では会館へ直接、安置をご希望する方が増えていますが、故人様の生前のご希望など踏まえて、決定し葬儀社へ確認しましょう。
2. 親族・近親者への第一報
次に、親族や近親者への訃報連絡を行います。配偶者→子→兄弟姉妹→親しい親族の順に、逝去日時・通夜葬儀の予定・詳細は追って連絡する旨を簡潔に伝えます。連絡役を1〜2名頼むと、喪主の負担が軽くなります。
3. 菩提寺の確認や宗教関係の確認
仏式の場合ですが、菩提寺がある場合はお寺へ連絡し、葬儀の依頼をします。その後、枕経をしていただいた後、葬儀日程の決定となります。仏式の場合の一例をあげましたが、宗教関係の信仰がある場合は、詳細を決める前に事前に連絡をなさってください。また、菩提寺がない場合は、仏式・神式・キリスト教式・無宗教式などを葬儀社と決めます。わからないことは葬儀社に任せて構いません。
喪主になった直後は、この3つを押さえるだけで動きが明確になります。安置先、訃報連絡、宗教・宗派の確認を終えたら、次は葬儀の日程や会場の調整に進みましょう。
亡くなった当日にやること(1日目)
ご逝去直後は、手続きと初期対応が中心です。すべてを完璧に決める必要はありません。大枠を固めることに集中しましょう。
-
1
死亡診断書(または死体検案書)確認
病院や施設より診断書を受け取り後、お名前・死亡日時を確認し、火葬手続きのため葬儀社へ預けます。こちらの書類は火葬許可申請に必須です。後日の手続きで必要になる場合があるため、診断書のコピーを葬儀社から受け取っておきましょう。
必須書類
原本の管理に注意
TIP:原本は湿気や折れに注意し、クリアファイルで保管すると安心です。
-
2
葬儀社への連絡と搬送・安置先の確定
病院から自宅または会館への搬送を依頼します。会館を選ぶ場合は霊安室の面会可否や面会可能時間を事前に確認しておきましょう。
搬送手配
安置場所の選定
TIP:夜間・早朝の搬送対応の有無や、面会時の持ち物も併せて確認しておくとスムーズです。
-
3
通夜・葬儀の日程調整
葬儀社担当者を交え、ご家族の都合だけでなく火葬場の予約状況や僧侶のご都合を踏まえて調整し、日程を決定します。
火葬場の空き確認
僧侶の予定確認
TIP:仮押さえの可否・キャンセル規定も確認しておくと予定変更時に安心です。
-
4
親族・近親者への一次連絡
逝去日時・通夜葬儀の予定・詳細は後報を簡潔に伝えます。連絡役を1〜2名指名して分担すると漏れを防げます。
一次連絡
連絡網の分担
テンプレ例:「◯月◯日◯時ごろ逝去。通夜・葬儀は◯日予定、詳細は確定次第ご連絡します。」
-
5
葬儀社との打ち合わせ
お葬儀の希望や予算の目安を共有します。細部(返礼品・会葬礼状・供花など)は翌日以降でも問題ありません。
希望整理
概算見積
TIP:宗派・会場候補・想定参列者数・写真データの有無などをメモしておくと打合せが早く進みます。
チェックポイント:この日は“大枠”を固める日。細部は2日目に。連絡や手配は喪主一人抱え込まず、家族で分担する。
通夜の前日までにやること(2日目)
2日目は、式の運営にかかわる具体を詰める日です。「誰が」「何を」担当するかを早めに決めるほど、当日の負担が軽くなります。
-
1
葬儀社との詳細打ち合わせ
式場レイアウト・遺影写真・祭壇/生花・返礼品・会食・会葬礼状・音楽/映像の有無・会計方法を決定。見積書で金額と内訳を確認します。
見積確認
祭壇・生花
映像/音楽
TIP:見積は「式場費・祭壇・車両・返礼品・料理」など大項目別の内訳と、差額が出やすいオプションを事前確認。
-
2
会葬者リストの作成
親族・友人・勤務先・近所ごとに整理。弔辞・お別れの言葉を希望する方がいれば事前依頼。弔電・供花の取りまとめ役を決め、弔電の読み上げ順等の希望は葬儀社へ伝えます。
連絡網整備
弔電・供花
読み上げ順
TIP:肩書き表記や敬称を統一し、最新の連絡先を確認。共有スプレッドシートの利用が便利です。
-
3
役割分担の決定
受付・会計・案内係・弔電整理・供花札確認・記録係などを信頼できる人に依頼。喪主は全体調整や来客対応、会葬御礼の準備に専念できるよう体制を整えます。
受付/案内
会計/記録
供花・弔電
TIP:役割ごとに連絡先と当日の集合時間を共有。簡単な動線図や役割メモを用意すると安心です。
-
4
式服や小物の準備
喪服・数珠・黒い靴・ハンカチ・予備マスク・筆記具・封筒・メモ帳などを家族分用意。即日返し予定なら手提げ袋も確認します。
喪服/数珠
筆記具/封筒
手提げ袋
TIP:会場の冷暖房や靴の指定(ヒール不可等)がある場合は事前に確認しておきましょう。
-
5
弔問客への案内
日時・会場・交通手段・駐車情報を簡潔に案内します。必要に応じて面会可能時間や会場内の動線も補足します。
日時/会場
アクセス/駐車
テンプレ例:「◯月◯日(◯)◯時〜/◯◯会館◯階。駐車◯台、公共交通:◯◯駅より徒歩◯分。地図URL:◯◯」
実務アドバイス
- 受付・会計は慣れた人に依頼し、釣り銭・筆記具・名簿を準備。
(家族葬の場合は参列者が限られるため、受付や案内を簡略化できる場合もあります)
- 休憩と食事を意識して確保。体調管理も喪主の大事な役割。
- 人手が足りない場合は、葬儀社スタッフに受付や案内を依頼することも可能です。
通夜・葬儀当日にやること(3日目)
通夜・葬儀当日は、これまで準備してきた内容を形にする日です。喪主は式全体の中心となりますが、すべてを自分で行う必要はありません。葬儀社や周囲の協力を得ながら進めましょう。
-
1
式前の最終確認
座席数の確認、受付・会計・案内係の配置、供花の並び順、弔電の拝読順位(会社名・お名前の確認)などを最終チェック。焼香手順/焼香順番、喪主が会葬御礼を述べる位置も予め確認しておくと安心です。
座席/動線
供花/弔電
焼香順
TIP:式場図に役割と導線を書き込み、受付・案内係と共有すると当日の迷いが減ります。
-
2
挨拶の準備
通夜・葬儀それぞれの挨拶文を確認。短くても感謝が伝わる内容で十分です。時間指定がある場合は目安(例:1分程度)に収まるよう整えます。
挨拶文確認
所要時間
ひと言例:「本日はご多用の中お運びいただき、誠にありがとうございます。生前のご厚誼に深く御礼申し上げます。」
-
3
式進行中の対応
基本進行は司会がリードします。喪主は落ち着いて焼香や会葬御礼を行い、急な確認事項は係へ伝えて調整します。
司会主導
喪主対応
TIP:ハンカチ・水分・予備の挨拶メモを手元に。体調優先で深呼吸を。
-
4
火葬場での対応
控室での過ごし方や飲食の可否を事前確認。収骨の際は案内に従い、ご遺骨・お位牌・遺影写真をどなたが持つか事前に決めておくとスムーズです。
控室/飲食
収骨の段取り
TIP:ご高齢の方やお子様の同席可否、移動距離や待ち時間も確認しておくと安心です。
-
5
御礼と事後対応
即日返しを行う場合は香典返し・会葬礼状を用意。弔電・供花への御礼は後日はがきや電話でも構いません。香典帳・会計の整理は体調を整えてからで大丈夫です。
会葬御礼/返礼
弔電・供花御礼
会計整理
TIP:返礼や御礼の目安時期をメモ化し、代表者と分担すると負担が軽くなります。
実務アドバイス
- 長時間の式となるため、喪主自身の休憩や水分補給を忘れずに。
- 家族葬の場合は、進行や案内が簡略化されるため、より落ち着いた雰囲気で対応可能。
- 感情が大きく揺れる場面でも、深呼吸してゆっくり話すことが安心感につながります。
3日間を乗り切るための心構え
突然の喪主は、誰にとっても大きな負担です。「弱音を吐いてはいけない」と気負いすぎる必要はありません。わからないことがあって当然です。全部を一人で抱えないこと、わからないことはその場で確認すること、睡眠と食事を軽視しないことが大切です。周囲の助けを受け入れる姿勢は、喪主としての大切な力です。
もしもの時に備えてできること
身近な方の「もしも」の時は「まだ先のこと」と感じる方も、できる範囲の準備が心の負担を軽くします。まずは事前相談の活用をご検討ください。
式の流れ、費用の目安、会場の雰囲気、火葬場の予約状況などを知ることで不安が軽減されます。必要書類と連絡先の整理も有効です。健康保険証、印鑑、基礎年金番号、勤務先・学校・親族の連絡先、菩提寺の情報などを1箇所にまとめておくと安心です。
初めて喪主を務めるあなたへ
突然の訃報は、誰にとっても戸惑いの連続です。安置先・連絡・宗教の3点をまず確認し、1日目は大枠の方針、2日目は役割分担と詳細、3日目は挨拶と進行の最終確認という流れを知っておくだけで、行動は確かになります。
わからないことはその場で相談し、周りの力を借りながら、故人らしいお見送りを整えていきましょう。仙台典礼では、初めて喪主を務める方や急なご葬儀にも安心して臨めるよう、事前相談から当日の運営まで丁寧にサポートしています。
費用や日程のご相談だけでも承りますので、もしものときやご準備の際には、どうぞお気軽にご相談ください。